医師や看護師に、認定医や専門医、認定看護師などの制度があるように、理学療法士にも『認定・専門理学療法士制度』があります。
今回は、『認定理学療法士』とは何か、そのメリット・デメリットも含め解説していきます。
認定理学療法士とは
まず、認定・専門理学療法士制度とは、理学療法士協会のホームページで以下のように記載されています。
・「登録理学療法士」を基盤とし、自らの専門性をさらに高めたい理学療法士への動機づけとなる「認定理学療法士」・「専門理学療法士」の制度を構築します。
・認定・専門理学療法士制度は、より専門性の高い臨床技能を有する「スペシャリスト」、いわば個性の育成プログラムです。
とされており、言い換えると、多種多様な理学療法対象分野の中で、専門性の高いスペシャリストを育成する制度となります。
認定理学療法士の分野
認定理学療法士には以下の21分野あります。
- 脳卒中
- 神経筋障害
- 脊髄障害
- 発達障害
- 運動器
- 切断
- スポーツ理学療法
- 徒手理学療法
- 循環
- 呼吸
- 代謝
- 地域理学療法
- 健康増進・参加
- 介護予防
- 補装具
- 物理療法
- 褥瘡・創傷ケア
- 疼痛管理
- 臨床教育
- 管理・運営
- 学校教育
認定理学療法士のメリット・デメリット
認定理学療法士を取得することで以下のメリット・デメリットが考えられます。
【メリット】
・取得分野の専門性の向上
・給与面で資格手当が付く職場あり
・転職活動時に認定資格は武器になりやすい
・飽和状態になりつつある理学療法士において認定資格は一つの武器
・認定理学療法士に馴染みのない職場では重宝されやすい
【デメリット】
・現在の医療制度では、認定理学療法士資格に対する診療報酬無し
・認定資格取得までの研修会や学会参加での出費
・業務時間後や休日での勉強時間の確保
このように、認定理学療法士は医師や看護師のように診療報酬におけるインセンティブを得るのは難しいため、認定資格の取得は意味を持たないと思われがちです。
しかし、自分の得意な分野の専門性の向上や、職場によっては給料up、転職活動で武器になるなど少なからず良い面もあると思われます。
認定理学療法士の取得者数
認定理学療法士取得者数は、2024年3月31日現在14,974名となっています。
日本理学療法士協会の総会員数が139,556名のため、認定理学療法士取得者は約10%になります。
分野別に見ると、運動器、脳卒中、呼吸、地域理学療法、循環、スポーツ理学療法、介護予防、代謝、管理・運営、発達障害の順で上位10位を占めており、その他の分野が10位以下に続きます。
経験年数別で取得者数を見た場合、10~20年が最も多く、その次に10年以内、20~30年、30年以上となります。
詳しい認定理学療法士取得情報に関しては、日本理学療法士協会のホームページをご覧ください。
認定理学療法士を取得するための条件
認定理学療法士を取得するためには、認定試験に合格する必要がありますが、認定試験を受験するためには以下の要件を満たす必要があります。
①登録理学療法士であること
②日本理学療法学術研修大会に参加すること
③指定研修カリキュラムを受講すること
④受験科目の臨床認定カリキュラムを受講すること
これらの要件を全て満たすことで認定理学療法士の認定試験を受験することができます。
①登録理学療法士
➤登録理学療法士は前期研修と後期研修を受講し、かつ前期研修が最短履修期間が2年、後期研修が最短履修期間が3年となっているため、受講修了まで最短でも5年要することになります。
②日本理学療法学術研修大会
➤日本理学療法学術研修大会は、年に1度開催されている学術大会で、2024年からは現地開催のみとなっています。こちらに参加することで学術大会参加の要件は完了になります。
③指定研修カリキュラム
指定研修カリキュラムは、認定理学療法士の認定試験を受験する方が全員共通で受講しなければならない研修になります。
指定研修カリキュラムは、e-ラーニングで12科目の受講し、それぞれの小テストに合格することで受講が完了になります。
④臨床認定カリキュラム
認定研修カリキュラムは、自分が受験する認定項目のカリキュラムを選択して受講する必要があります。
臨床認定カリキュラムは、受講する教育機関によって、現地開催かオンライン受講に分かれています。臨床認定カリキュラムは、必須科目が15項目、選択科目8項目の中から5項目を受講し完了となります。
認定理学療法士の認定試験に向けて
最後に、認定試験は臨床認定カリキュラムのシラバスに記載されているように、かなり幅広い範囲が出題範囲になっています。
出題内容は広く浅くといった感じで、普段から受験分野に特化した現場で勤務されている方は、そこまで難しくないかと思われますが、関りの少ない方には少し受験勉強が大変かと思われます。
2024年度の出題内容にも多くみられたのが、ガイドラインの内容が科目によって多く出題されていました。
受験した自分の感想としては、臨床認定カリキュラムの内容に沿って基礎的な内容の勉強に加え、ガイドラインの勉強も必要だなと感じました。
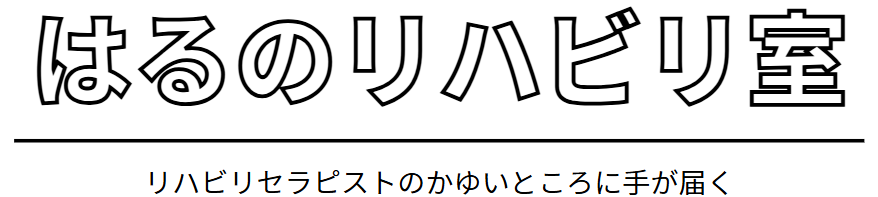
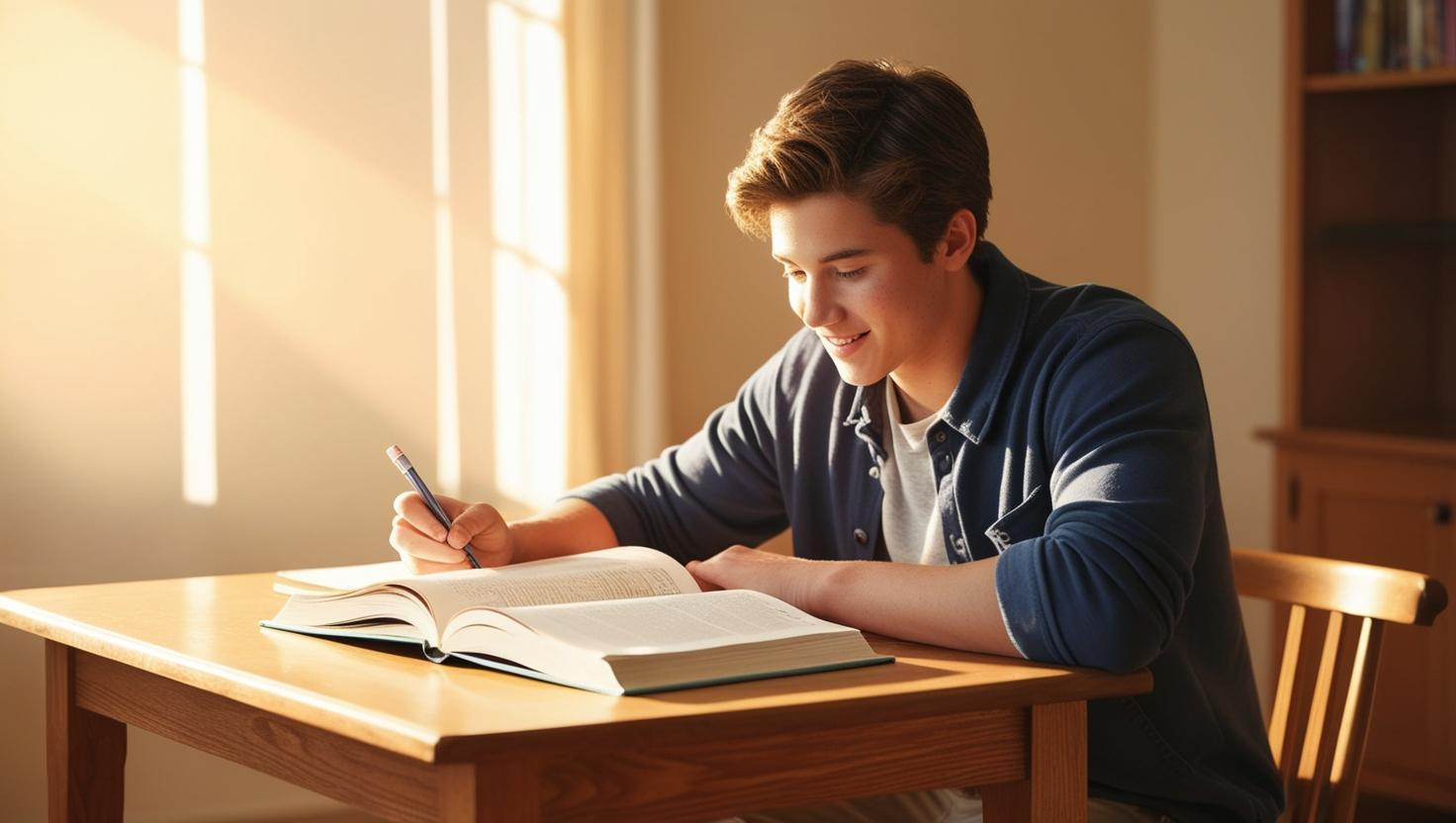





コメント